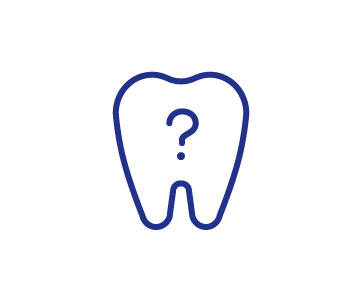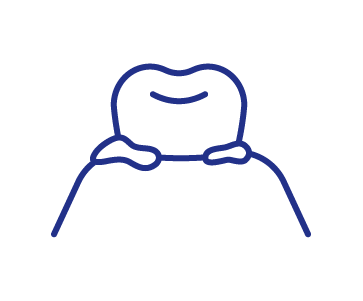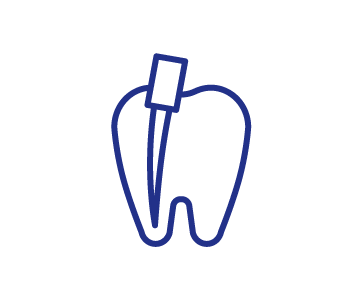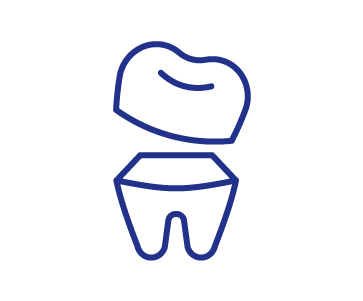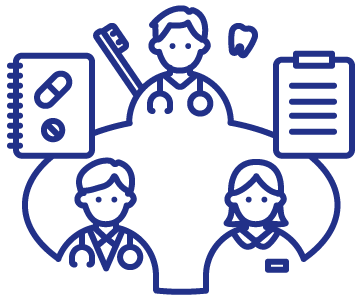診療案内 Treatment
冷たいもので歯がしみる
冷たいもので歯がしみる場合、むし歯や歯磨きのしすぎ、歯ぎしりなど何らかの原因で歯の表層を覆っているエナメル質が部分的にでも削られ、エナメル質の内側の象牙質がむき出しになることで起こる知覚過敏である可能性があります。象牙質には神経からの管が無数に伸びて歯の神経と繋がっているので刺激に対して敏感となり、冷たいものなどの刺激が管を介して神経に伝わり、キーンとしみたりするということが起こってきます。また、歯槽膿漏で歯茎が痩せてしまった場合も、歯茎の中の歯にはエナメル質がないので、象牙質が露出して知覚過敏を生じてしまいます。
知覚過敏について詳しくは下記の院長ブログをご覧ください。
甘いもので歯がしみる
甘いものがしみる場合、多くは銀歯などの詰め物や被せ物の下がむし歯になっていることが多いように感じます。詰め物や被せ物の下なので、よほど大きく進んでいない限りは肉眼では見えず、レントゲンでも写らないこともありますが、症状があれば詰め物や被せ物を外して中の状態を確認したほうがいいかもしれません。
温かいもので歯がしみる
温かいもので歯がしみる場合、神経に何らかの原因で炎症が起こっていることがほとんどです。冷たいもので歯がしみる場合は、大抵が知覚過敏であまり心配はいらないのですが、その状態から一段階進んで、神経に炎症が及んでしまった場合、温かいものでしみる感覚が出てきます。その際、冷たいものを口に含むと痛みが治まるとおっしゃられる方も割と多くいるように感じます。このような症状が出てきた場合には、しみ止めの薬だけでは収まらず、残念ながら麻酔をして中の神経の処置をすることが、症状の改善のためには必要であることがほとんどです。
▼神経に達するような深いむし歯には、根っこの治療を行います
根っこの治療
歯がズキズキと痛む
歯がズキズキと痛む場合、大きく分けて神経に達するような深いむし歯であるか、あるいは根っこの先にばい菌が入って膿が溜まっているかのどちらかであることが多いです。いずれにしても根の中の治療が必要になってきます。
食事をしたり物が当たると歯が痛む
歯の神経に炎症がある場合や根っこの先に膿が溜まっている場合、また、歯槽膿漏で歯が揺れる場合も、食事をしたり物がその歯に当たったり、グッと強い力がかかると痛みを感じる場合があります。
歯茎が腫れて痛みがある
歯茎が腫れているということは、多かれ少なかれ歯茎あるいはその下の骨の中に膿が溜まっているということです。歯茎あるいは骨に膿を生じる原因としては、根っこの中にばい菌が入っているか、歯槽膿漏がほとんどです。
歯が噛むたびに動いて噛めない
歯が噛むたびに動いて噛めない場合、歯槽膿漏で歯を支えている顎の骨が溶けてぐらつきを生じているか、あるいは歯の根元の部分から深いむし歯になって歯の頭だけが折れかかって動いている場合もあります。
▼歯槽膿漏の治療につきましては、こちらの診療案内をご確認ください
歯槽膿漏
歯茎にニキビのようなものができている
歯茎にポツッとできるニキビのようなものは、大抵、歯茎の膿の出口であることがほとんどです。歯茎に膿を溜める原因としては、歯槽膿漏と根っこの中の感染がありますが、歯槽膿漏ではどちらかといえば深い歯茎の溝から自然に膿が出ていく印象があり、膿の出口を歯茎に作る原因としては根っこの感染が多いように思います。
▼歯茎の膿の出口や根っこの治療につきましては、こちらの診療案内をご確認ください
根っこの治療
歯に穴が開いている
歯に穴が開いている場合、虫歯で歯が溶けてしまったことによるものが多いです。穴の大きさや神経との位置関係によって、詰め物の治療あるいは根っこの中の処置となります。
歯と歯の間にものがよく詰まる
歯と歯の間にものがよく詰まる一番多い原因は、被せ物の歯と歯の間の部分が少し緩んできたことによるものです。その場合は被せ物を少しきつめに作り直せば、ある程度症状は改善されていきます。あとは歯と歯の間の部分に虫歯で穴が開いていたり、歯槽膿漏で歯と歯の間の歯茎が下がったりしても、ものが詰まりやすくなります。
▼被せ物につきましては、こちらの診療案内をご確認ください
被せ物・入れ歯(補綴治療)
口内炎がなかなか治らない
口内炎はその多くが栄養状態や歯、入れ歯等の刺激によってできてくるため、原因となっている刺激等を取り除くことによって、ほとんどは一週間もしないうちに治ってきます。しかし、これら原因を取り除いてもなかなか治らず、一ヵ月近く残ったままになっている口内炎の中には、少したちの悪い種類のものも稀にですが存在することがあるため、念のため歯医者を受診してしっかりと診てもらい、必要に応じて検査等をしていただくことが重要かと考えます。
▼なかなか治らない口内炎等は、患者様への負担の少ない細胞診をおすすめします
口腔外科(当院の治療:細胞診について)
顎の感覚に痺れがある
顎の感覚に痺れを感じる場合、大きく分けてその原因は炎症か腫瘍があげられます。顎の感覚を支配する神経は下顎の骨の中を前後に走っているため、その骨の部分に炎症あるいは腫瘍があると、走っている神経が刺激されてピリピリと痺れたような感覚が出現してくることがあります(患者様によっては虫が走っているような感じと表現される方もいらっしゃいます)。いずれにしても、何もないのに顎の感覚が痺れてくるということはまずないので、炎症にしろ腫瘍にしろ、しっかりとどちらが原因なのかの検査を受けた上での対応が必要になってくるかと思います。
▼顎の感覚に痺れを感じる場合は、口腔外科の受診をおすすめします
口腔外科